![小説を通じて考える、本当の“共感” ──物語をつくる人#01 平野啓一郎さん[後篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2018/11/hirano-2_eye.jpg)
小説家や脚本家が「物語をつくる理由」を探っていく連載企画、「物語をつくる人」。第1回は、小説家の平野啓一郎さんにお話を伺います。
前篇では、平野さんの物語の原体験や小説を書き始めた頃のお話、現代における小説の難しさについてなどをお聞きしました。後篇は、「小説だからできることとはなにか?」の核心に迫ります。
(前篇はこちら)
取材・文=志村優衣(SPBS)
写真=敷地沙織
考え続けてきた「自分とはなにか」という問い
──平野さんは、「分人主義」という考えを提唱されています。人間には、「たった一つの本当の自分」なんてものはなく、対する相手ごとに違う人格=分人があり、それら分人の集合体が自分であると。『ドーン』*1でその考えが登場し、第三期を通して分人主義について深掘りされていますが、第四期に入っても、大きくアイデンティティというテーマは通底されていますよね。
平野:そうですね。だから苦肉の策として、第三期を「前期分人主義」、第四期は「後期分人主義」って呼んでます(笑)。前期は人間の「自己意識」にフォーカスして、自分の多面性を発見していく過程を描いていました。
結局、分人って、誰かとの関係や住んでいる環境など、外部からの影響がすごく大きい。だから後期はその外部環境によって、人間がどのように変わって、人生が翻弄されているかという、運命的な視点がより強くなっています。
──最新作『ある男』*2には、「在日三世」や「殺人犯の息子」という出自の人物が登場していますね。
平野:そういったカテゴリの中に自分が属していること、周りからカテゴリを当てはめられることが、運命にどう影響するのか?というのが、一つのテーマになっています。
*1『ドーン』……人類初の火星探査に成功し、一躍ヒーローとなった宇宙飛行士・佐野明日人が、アメリカ大統領選挙を揺るがすスキャンダルに巻き込まれていく。「分人」という概念を提唱した長編作品。2009年講談社刊。Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。
*2『ある男』……平野啓一郎さんの最新長編小説。「死んだ夫がまったくの別人だった」という奇妙な相談を受けた主人公の弁護士・城戸が、その真相を探る過程で、自分の人生や愛の本質について見つめ直していく物語。2018年文藝春秋刊。

──アイデンティティの問題には、昔から興味があったのですか?
平野:ある時期から、周りのみんなが僕のことを「変わってる」って言い始めたんですよ。実際クラスで話し合いをしても、「当然こうだろ」と思って僕が言ったことにほとんどの人が賛同しないことが多くなってきた。
僕は割と社交的だったから、それでもクラスの友だちとは仲良くしていたんですけど、彼らが休み時間にしゃべってることは、あんまりおもしろいと思えなかった(笑)。そういう中で、「自分とはなんなのか?」を考えるようになったんです。それに、たくさん本を読む中で、自宅で本を読んでいる自分と、学校にいるときの自分は違うという感覚を持つようにもなった。
あと、就職を考えなくてはいけない時期に、「自分が本当にしたい仕事はなにか?」を突き詰めていくと、「自分とはなにか?」という問いにならざるを得なかった。その問いの答えを出すことが、簡単じゃなかったんですよね。それでやっぱり、アイデンティティの問題について悩みました。

──小説を通して、そうした「自分とはなにか?」を考えることを促すような問いかけを読者にもしている?
平野:いや、あくまで小説の一つのテーマであり、要素に過ぎないので、それが大きな目的ではないですよね。そのテーマとは関係ない作品もいろいろありますし。ただ、そのときどきで自分が関心のあることで、同時代の人にとっても重要な問いはなにか、というのは考えます。
多くの近代小説はアイデンティティの問題をめぐって書かれてきたという歴史もあるし、自分自身としても悩むことが多いテーマだったので、たまたま、いまそこにフォーカスしている感じですね。
“具体”を描ける小説だからできること
──では、平野さんが小説を書く理由、小説を通してやりたいことは、なんなのでしょう?
平野:うーん……。難しいですね、理由はいろいろありますから。職業作家だから、お金稼ぐのも一つだし(笑)。
でも、突き詰めていくと、「自由で愛に満ちた人間像」を社会が獲得していくうえで、小説というものが有意義だと考えているから、というのはありますね。
──自由で愛のある世界を実現したい?
平野:「世界の実現」というか、「人間像」なんですよね。そういう人間像とはどういうものなのかを、社会は模索していくべきだと思うんです。
──そのためには、小説でしかできないことがある。
平野:と、思います。小説って、一度にいろいろな登場人物を描けるし、人間同士の関係性も描ける。なによりも、具体的だから。
「こういう風に生きていくべきだ」というような抽象的な命題は、人を納得させやすいんですよね。でも、実際の生活でその通りに生きようとすると、いろいろ問題が起こることがあるじゃないですか。
その点小説は、大きなテーマを語るにしても、生活を具体的に描いていく。すると、どうしたってその通りじゃ上手くいかないことも出てくるし、「じゃあどうしたらいいか?」を考えなきゃいけない。それが、小説というジャンルの便利なところ。
「わかる」がはらむ暴力性
平野:それに、人間ってエモーショナルなところから動かされないと、なかなか考え方は変わらない。『ある男』でも書いていますが、他者の物語を通すと、自分だけでは処理できなかった問題も違うアプローチで見つめられて、孤独や苦悩が慰められることがある。そういうのが、小説を含めたフィクションの機能だし、自分が小説を読んできた理由もそこにあると思います。
あと、登場人物にすごく共感して、忘れられない小説があったりしますが、その人が僕に似てるかというと、必ずしもそうじゃないんですよね。それが、フィクションのおもしろいところだなぁと。

──似ているから共感する、というわけではない。
平野:ではないですよね。でも、「気持ちわかる!」っていうのでもないんですよ。その登場人物の人生に触れることで、自分がすごく揺さぶられて、自分が考えていたことや悩みが、変容していくっていうんですかね。そうして、自分の考えや価値観が、深まったり広がったりしていくことが、共感するということなのではないでしょうか。
──共感というと、「うん、わかる、わかる〜!」ということだと思われがちですけど、決してそれだけではないですよね。そして小説を読むと、「共感って『わかる』だけじゃない」ということが見えてくる。
平野:「わかる、わかる」っていうのは、ちょっと暴力的なところもありますよね。自分がすごく悩んでいて、それを他人に打ち明けたときに、「めっちゃわかるわ〜」って言われると、ちょっと抵抗あるっていうかね。「わかられてたまるか」みたいな(笑)。
だからといって、「全然わかんない」って言われても、「人が相談してるのに、腹立つわ」ってなりますし(笑)。やっぱり、ある程度のところまではわかってもらいたい気持ちがあるし、相手のこともわかりたいとも思うけど、「最後の最後はわからない」っていうのが、相手に対する、相手の他者性に対する最低限の配慮だと思うんですよね。その配慮がないと、共感も暴力的なものになる。だから、共感って難しいですよね。
小説を書いていても、自分が想像した登場人物にもかかわらず、「本当のところ、この人はどう思っているのか?」がわからなくなることがあるんです。それは、決して設定が甘いからではなくて。僕は作者だから、その人物の行動の動機を「たぶんこうだ」と思って書いているんだけど、その人が他人のように感じられて、「本当は違うんじゃないか?」という気がしてくる。そういうときは、その架空の人物と本当に向き合っているようなリアリティを感じるし、人物造形がうまくいってるんじゃないかって思います。
2020年代に人は小説を読むのか?
──では最後に、平野さんの今後のお仕事や次回作の構想について教えてください。
平野:近々決まっている大きい仕事が三つあって。一つは、『カッコいい論』。「カッコいい」って誰でも知っている言葉だけど、あんまり真面目に考えてきていないんですよね。だけど、20世紀後半以降の文化をきちんと理解するには、「美」「崇高」とも違う、「カッコいいとは何か?」がわからないと、ロックもジャズも、ファッションも、何も語れないはずなんです。だから、その「カッコいい」について、人類学的な視点から考えて書こうとしています。
あとは、2020年に三島由紀夫が没後50年を迎えるので、それに向けて『三島由紀夫論』の執筆の準備をしているのと、来年の夏ごろからは小説の新聞連載が決まっています。

──その作品は、第四期に分類されるのでしょうか?
平野:うん、(第四期と第五期の)狭間ぐらいですね。いま、2020年代がどういう時代になるかということを前提として考え始めているんです。そうすると、やっぱりけっこう辛い時代になるんじゃないかという気がしていて。オリンピックも終わって我に返って、きっと土地の値段も下がっていくし、少子高齢化もシリアスになっていくでしょ。温暖化ももっとひどくなると言われてる。
そういう時代に、それでも人が小説なんかを読みたいと思うのなら、その理由は一体なんなのかというのを、かなり考え抜かないと読まれなくなると思っています。だから、そのことを考え出すとね、何を書こうかなって……。
存在論的なレベルでアイデンティティの問題を考えられないかなとは思っていて、アイデアはいくつかあるんですけど、ちょっとそれじゃダメなんじゃないかな、とか。もう一つなんか突き抜けたテーマを考えたくて、ちょっと迷っているところです。
──長い目で見たときに、やりたいことや目標はありますか?
平野:中・長期的には、特にないんですけど……まあ、あんまり仕事を詰めすぎないのが当面の目標ですね(笑)。
──ゆとりを持って(笑)。
平野:ゆとり世代ではないんだけど(笑)。3年に1作ぐらいのペースがいいんですよね。社会的にも、ブラック企業問題とかもあって、ワーカホリックは減ってきているし。僕も20代、30代のときは、がむしゃらに仕事するしかなかったですが、いまはもう少しじっくり、間隔を空けて仕事をしたいなと思ってます。
──ではまずは、直近の3作を楽しみに待っています!
平野:ありがとうございます。


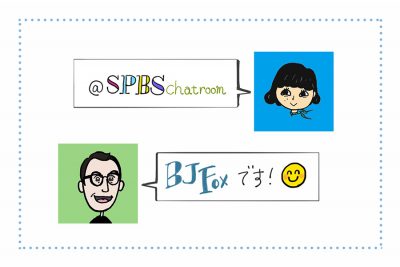

![物語の船で知らない世界にたどり着きたい──物語をつくる人#02 村田沙耶香さん[後篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2019/01/murata-2_eye-400x267.jpg)
![小説の神様に向き合い続ける作家──物語をつくる人#02 村田沙耶香さん[前篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2019/01/murata-1_eye-400x267.jpg)

平野啓一郎(ひらの・けいいちろう)さん
1975年生。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』で第120回芥川賞を受賞。以後、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。著書は小説に、『葬送』、『決壊』(芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞)、『ドーン』(ドゥマゴ文学賞受賞)、『かたちだけの愛』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』(渡辺淳一文学賞受賞)、エッセイ・対談集に『私とは何か 「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『考える葦』などがある。2018年9月に新作長編小説『ある男』を刊行。
●公式サイト