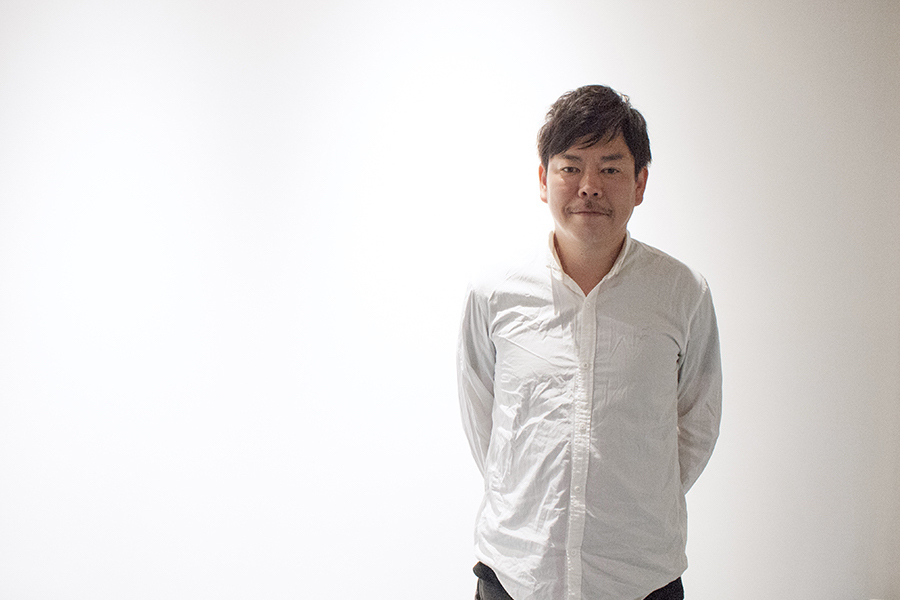
「雑誌『TRANSIT』の編集長が交代するらしい──」
そのニュースを聞いたSPBSの代表が、前編集長の加藤直徳さんに会いにいったのが2016年の9月。そこで、「SPBSでZINE(*1)を出しませんか?」と話を持ちかけ、加藤さんから出たアイデアが「これから創刊する雑誌をつくる過程を追う連続ZINEシリーズ」というものでした。そこから、加藤さんが所属するデザイン会社SOUP DESIGN(現・BOOTLEG)とSPBSの共同プロジェクトがスタート。2017年6月に『ATLANTIS zine』の1号目を発売しました。
毎号、実際の雑誌制作の過程が編集長の思考と葛藤とともにつまびらかにされていくZINEシリーズも、5月26日(土)発売の06号でとうとう最終号。7月末には待望の本誌『ATLANTIS』が創刊となります。約1年9ヵ月にも及ぶ『ATLANTIS zine』プロジェクトを完走し、新たな挑戦の真っただ中にいる加藤さんに、いまの率直な気持ちを伺いました。
*1 ZINE……少部数で発行される出版物のこと。リトルプレス。「Magazine(雑誌)」が語源。
取材・文・写真=志村優衣(SPBS)
ロバート・フランク展の学生ZINEが気持ちを後押し
──『ATLANTIS zine』もとうとう最終号ですね。お疲れさまでした。一昨年、SPBSから「一緒にZINEをつくりませんか?」という提案をしたとき、率直にどう思いました?
加藤:日本でも海外でも、ZINEのムーブメントがあることを知ってはいましたが、実は、あまり価値を見いだせていませんでした。学生のときは自分でフリーペーパーをつくっていたこともありますが、社会人になり雑誌をつくるようになってからは、「お金がないからこれくらいのクオリティで……」というような“完成形じゃない”冊子を見ると、「買う価値あるのかな?」と思ってしまって。自分のなかで「ZINE」の定義が明確になっていなかったし、正直、最初は迷ってましたね。
──その思いが変わったきっかけは?
加藤:2016年の11月に、東京藝術大学で開催されていたロバート・フランクの展覧会(*2)で、開催までの日々を日記のように綴った、展示のプロローグ的なZINE(*3)が配られていたんです。「展覧会の裏側を見せる」ということを立体的かつ徹底的にやっていた
「新しい雑誌ができるまでを追っていくZINE」というアイデアはそのときすでに持っていたんですが、そのロバート・フランク展のZINEを見たことで確信を持てました。ZINEのなかで『ATLANTIS』への道のりを立体的に見せていくことで、創刊号が出たあとにZINEを読み返しても楽しめるようなものになるし、それなら読者に価値を見いだしてもらえるんじゃないかと。

新雑誌創刊を目指しながら、初体験のZINE制作に挑戦することには大きな不安があった、と振り返る
──そのときすでに、新雑誌『ATLANTIS』の構想は固まっていたんですね。
加藤:いや、新しい雑誌を立ち上げることは決めていたんですが、何年後になるかは分からなかったし、具体的なことはまったく。だから、ZINEをつくることにすれば、強制的に納期が決まるというか、雑誌の制作が進むんじゃないかという思いもありましたね。
──では、ZINEをつくり始めた時点では、ZINEの最終号がどうなるか、雑誌がどんなものになるのかっていうのは……。
加藤:分からなかったですね。本当に、ZINEをつくりながら同時進行で、雑誌の制作を進めていったので。
*2 「Robert Frank: Books and Films, 1947-2016 in Tokyo」。写真界の巨匠ロバート・フランクが、世界最高峰のアート出版社・STEIDLの創業者であるゲルハルト・シュタイデルとともに企画した、ロバート・フランクのこれまでの活動を振り返る展覧会。世界50都市を巡回し、東京展では東京藝術大学の学生が、イベントの企画・運営に参画した。
*3 『Students at TUA: Effort and Document, May-November, 2016』。展覧会の東京藝術大学オリジナルカタログで、学生たちが制作に携わった。
雑誌づくりの基本に立ち帰ることができた
──『ATLANTIS zine』は01号〜06号にかけて、徐々に判型が大きくなっていきます。このアイデアはどのように生まれたのですか?
加藤:中身が雑誌に近づいていくに従って、ZINEも中綴じになって、平綴じになって、形も大きくなって……と成長していくことで、いままでにないものになるかな、と。「雑誌制作の裏側」というテーマ自体が非常にニッチなので、そういったZINEのコンセプトにも魅力を感じてもらえたらいいなと思いました。
01号・02号は、「頭のなかで考えを育てていく」という目には見えない部分を追った内容なので、デザインが洗練されていたら、どうも噛み合わない。だから、タイトルを手で書いたり、頭で考えたことを手書きで図式化して載せたりと、アイデアが育っていく過程をアナログ的に見せるようにしました。自分でも手を動かして、考えを定着させるような作業がしたくて、装本も、紙を手で折ってゴムで留めるようにしたり。
──誌面レイアウトも毎号違いますよね?
加藤:『ATLANTIS』で採用するかもしれないデザインをテストしていました。せっかく6通りのデザインが組めるので、本文の文字の大きさや字間、フォントを変えることで、見え方がどうなるのかを試しながら、自分がどういう見せ方をしたいのかを考えてましたね。

6号かけて『ATLANTIS zine』はここまで育った

本文は1段組から3段組まで。写真の使い方も毎号変わっている
──最終的にこの6冊のなかに、『ATLANTIS』創刊号のデザインのベースになったものはあるんですか?
加藤:結局、まったく違うものになりました。でも、いろいろ試したなかで、削ぎ落とした部分とか、足していった部分があるので、この6冊がなければ、創刊号のデザインも生まれなかったんじゃないかと。
──取材と執筆作業は、基本的にはすべて加藤さん一人でやっていたんですよね。
加藤:そうですね。取材相手の連絡先を調べたり、テープ起こしをしたり、くらいはアシスタントに手伝ってもらいましたが、それ以外は全部自分で。
「編集長に会いにゆく」という連載に出てもらったのは、面識がない人がほとんどでした。まだ雑誌ができていない状態、つまり、自分の名刺代わりになるものがない状態で、話を聞きたい人に連絡して、自分の想いを伝えて、会いにいって言葉を吸い上げ、誌面に反映させる。スタート地点に戻ったというか、編集者としての一番基本に立ち帰れたので、よかったなぁと思います。『TRANSIT』時代の後半は、編集“長”として仕切る仕事に徹してしまい、編集“者”としての仕事をサボってしまっていたので。
──アポ取りも自分でやっていたんですね。
加藤:やっぱり、話を聞きたい人が自ら連絡するのは大事です。みんな忙しい人なので、アシスタントが企画書を送っても、「ふーん」って流して終わっちゃうと思うんですよね。04号に出てもらった都築(響一)さんは、長崎でトークショーがあると聞きつけて、そこまで会いに行きました。そこで、「後日、企画書送らせてください!」って。その場で渡すんじゃなくて。
──じゃあ、挨拶をするためだけに長崎に?
加藤:そう。昔、横尾忠則さんを口説いたときにも同じようなことをやりました。毎号、話を聞きたい人って「その人」しかいなかったんですよ。断られたら次の人探して、っていうのではないんで。
いまでも不安だし、毎日迷ってる
──『ATLANTIS zine』をつくるなかで、楽しかったことはありましたか?
加藤:ZINEをつくる作業、つまり雑誌を生み出す過程は、たとえて言えば、とっ散らかっているデスクをきれいにしていくようなもの。自分の頭のなかに、やりたいこととか、アイデアのメモ書きがいっぱいあって、それを一つひとつ、「必要なメモなのか」「もう捨てていいものなのか」って取捨選択していく。そうすると、やらなくてもいいのに固執していたものに気がついて、それを削ぎ落とすとやるべきことが分かって……と、頭の中が整理されていくのは楽しかったですね。だから、最初の頃は辛かったですよ。掃除と同じで、始めるまでは苦痛なんで(笑)。

06号「にも関わらず、ATLANTISを編む」には、加藤さんの雑誌づくりへの葛藤と迷い、それでも編集し続けることを選んだ理由が詰まっている
──「やらなくていいこと」とは?
加藤:自分がつくりたいと思うもの以外、すべて。「自分がつくるものを他人はどう思うだろう」「世間は受け入れてくれるだろうか」というような考え、要するに、マーケティング的な要素。他の雑誌を見て参考にしたり、流行っているものをリサーチしたりとかは、したくなかった。人に意見を聞くのも、自分がやりたいことを裏付けるため。
でもこれは、同時に怖いことでもあって。「(世間から)求められていないんじゃないか」「(読者が読みたいものを)まったく外してるんじゃないか」っていう不安は本誌のコンテンツを考えてるときもあったし、今でもある。
──その不安と引き換えに、自分のやりたいこと、つくりたいものは、どんどん研ぎ澄まされて、形が見えてきたんでしょうか。
加藤:うーん……。01号から06号まで、一つの一貫した流れがあって研ぎ澄まされていったというよりは、毎号、その1号の中でもあっち行ったりこっち行ったり、メトロノームのように、振れていた感じですかね。「これでいいのか」「いや、こっちの方がいいんじゃないか」って。いまでもまだ振れていて、集約できていない。自分がどんな雑誌をつくりたいのか、答えを出すためにZINEをつくったつもりなんですけど、より答えが分からなくなった。
──そうは言っても、もう雑誌の発売日は決めているんですよね?
加藤:そうですね、7月27日。いまはまだ、一つひとつのコンテンツを迷いながらつくっています。でも雑誌を完成させるには、自分がやりたいものを一度全部揃えて、全体を見る必要がある。荒い束になったときに、そこからスタートするんじゃないかな。それが大体、入稿の1ヵ月くらい前だと思ってる。
だからいまは、信じて集めている状態ですね。全体を組み上げて、いらないものを捨てていけば、自然と濃いものが残るんじゃないかなと思います。アートディレクター(尾原史和さん)とは、「絶対失敗できないから、考え続けるしかないよね」と話している。
世界中に読者はいる。あとは、自分がやるかどうか
──今回、雑誌の制作と並行して、Webメディアの立ち上げも検討していると聞きました。ずっと紙の編集をされていた加藤さんにとっては、新しい挑戦ですよね。
加藤:Webも立ち上げることは、最初から考えていました。
──どんなサイトになる予定ですか?
加藤:雑誌の延長線上にあるというよりは、まったく別のもの。『ATLANTIS』の本誌と同じテーマで、雑誌とは違うコンテンツを載せたいなと。
──雑誌に載せるものとWebに載せるものの違いは?
加藤:「プレイヤー」が違うっていうんですかね。雑誌に載せるコンテンツには、すべて企画から僕が関わるんですが、Webではこのテーマに共感した人に自由に参加してもらいたいと考えています。もちろんこちらで編集はしますけど、テーマに沿って写真集をつくる人がいてもいいし、絵を描く人がいてもいい。グッズをつくってWebで売ってもらってもいい。
──表現したい人が集まる、プラットフォームをつくるイメージなんですね。
加藤:プレイヤーをどう巻き込んでいくかを考えるのは、これからのミッションです。

加藤さんの所属するBOOTLEGは、オフィス1Fに新しくギャラリーもオープンする。DIYで絶賛施行中。そこでは定期的に写真家からの持ち込みを受け、若い才能を発掘していく予定という。これも、新しい挑戦だ
──雑誌の販売も自社で行うんですよね?
加藤:そうです、直販・買い切り(*4)で。書店に営業していきます。
──まだ世に出ていない雑誌を買い切るというのは、書店にとっても非常にリスクが高いことですよね。
加藤:でも、「とりあえずいっぱい仕入れて、売れなかったら返す」というやり方ではなくて、書店の人に「これは売れる」と思って仕入れてもらいたい。理想ではありますが、書店との間に「この本を、ここで、これだけ売る」という共通認識を持って、関係を築けたらと。中身が完成しないうちから営業にいかなくてはいけないので、自分でも不安はありますけどね。
──部数の目標はありますか?
加藤:まずは創刊号、部数はそれほど多くないですが、確実に売り切りたいです。
──大手ではない出版社で、直販で在庫をなくすというのは、簡単なことではないと思います。でも、もしそれが達成できたら、小さな出版社や書店にとっては大きな希望になる。SPBSも、そんな小さな出版社の一つなので、全力で応援しています。
加藤:ありがとうございます。
──『ATLANTIS zine』01号の「はじめに」で、これは「未来の編集者へのLetter」だと書かれていました。6冊を終えてみて、改めて、若い編集者や雑誌づくりをしたい人たちへのメッセージをお願いします。
加藤:いまは大手の出版社に就職しても、やりたい本がなかったり、自由に実験させてもらえなかったりと、昔より不自由な状況にあることは容易に想像ができます。雑誌の場合は特に、状況は厳しいかもしれません。でも、個々がスキルを磨いていけば、自分でメディアを立ち上げることができる時代でもある。世界に目を向けてみれば、ZINEのブームしかり、個人で完成度の高いものをつくっている人がいて、きちんと売れている。世界中に読者がいて、売れる時代だと信じているので、大きな組織にいてもいなくても、まずは編集スキルを磨いて、続けてほしいなと。好きなら続けていれば、問題ないよって。
──読者が減っているとは思っていない?
加藤:思ってないですね。全然、斜陽でもない。逆に、自分でつくれると思っている人が増えているとは思うので、そのなかで特別なものを生み出すには、きちんと学んでスキルを磨いておかないといけない。
でも、未来を想像して、諦める時代ではないというか。組織の力が弱まってきているからこそ、未来は自分に委ねられている。やりたいコンセプトを温めて、育てていけば、すごく大きな花を咲かせられる可能性がある。僕も40歳を超えてるけど、20歳代の若い子がつくったものも見ているし、海外ではすごいものをつくっている子も多い。組織も関係ない、年齢も国も関係ないとなったときに、残るのはコンセプト。自分がやりたいこと、伝えたいこと。それがまあ、しょぼいかどうかっていうのは、チャレンジした後にしか分からないから、まずは、諦めないでつくっていってほしいなと思います。
*4 書籍販売は一般的に、出版社と書店の間に「取次」と呼ばれる流通業者が入る。また、委託販売制度を採用する場合が多く、書店は一定期間を過ぎても売れなかった書籍や雑誌を取次に返本することができる。「直販」「買い切り」は通常の書籍と異なり、管理の手間が煩雑で、在庫リスクも負うことになるため、書店にとってはハードルが高い取引となる。







加藤直徳(かとう なおのり)
1975年生まれ。編集者。白夜書房に勤務していた2004年、トラベルカルチャー誌『NEUTRAL』を創刊。08年『TRANSIT』に改名し、講談社より刊行。16年9月発売の33号まで編集長を務める。現在は、株式会社ブートレグで、新雑誌『ATLANTIS』の創刊に向け準備中。