![小説の神様に向き合い続ける作家──物語をつくる人#02 村田沙耶香さん[前篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2019/01/murata-1_eye.jpg)
小説家や脚本家が「物語をつくる理由」を探っていく連載企画「物語をつくる人」。第2回は、芥川賞作家の村田沙耶香さんにお話を伺いました。
小学生の頃から小説を書いていたという生粋の「つくる人」である村田さんは、いつ頃から小説の世界に魅了され、どのようにその世界と向き合っているのでしょうか?
取材・文=志村優衣(SPBS)
写真=横尾涼
物語に100%本気で向き合う大人がいるなんて!
──まずは、村田さんの物語の原体験からお聞きしたいと思います。小さい頃から、よく本は読まれていたのでしょうか?
村田:そうですね、本は好きでした。私はニュータウンで育ったのですが、大きい本屋さんとか古本屋さんとかはあまりなくて、図書館や図書室の本を借りて読んだり、兄や母の買った本を読んだりしていました。幼稚園の図書室も好きでしたね。
──幼稚園にも図書室があったんですね。
村田:たしか、そうです。あとは近所の集会所の図書室とか。そこが、好きでしたね。いつも本ばっかり読んでいたのを覚えています。とはいっても、そんなに量を読むタイプではなく、同じ本を何度も読んでいましたね。
──その頃に何回も読んだ本には、どんなものがありますか?
村田:小学生のときに衝撃を受けたのはジュール・ルナールの『にんじん』です。
──どんなところが衝撃的だったのでしょう。
村田:それまでに読んできた話って、どこかにわかりやすい救いがあったんですよね。大人の思惑が透けて見えるようなものもありました。
それなのに『にんじん』はすごく絶望的で、そもそも主人公がとても残忍な側面を持っていたり、お母さんが実は愛してくれていました、という呪いみたいなハッピーエンドでもなく、最後まで悲しいまま。でも、「こんな絶望的な話を書く大人がいる」ということに、本の世界を信頼できるって思ったんだと思います。

──ハッピーエンドだけじゃないところに、現実を見出したのでしょうか?
村田:うまく言えないですけど、ハッピーエンドにすることで、子どもを大人の都合のいいように洗脳しようとしているんじゃなくて、この作者は100パーセント本気でこの物語に向き合っているんだろうなぁ、っていう感じがしたんだと思います。
──それって、小学校何年生くらいのことか覚えていますか?
村田:小学校3〜4年生じゃないかと思います。小学校1年生くらいのときは、「大人は子どもを都合のよい存在につくりあげようとしている」と思い込んでいて、伝記ばかり読んでいた時期もあったんです。「大人は大人にとって都合のいい話しか書かない」みたいな。
──小学校1年生で! 悟っていますね!(笑) そんな伝記しか読まなかった村田さんが、『にんじん』を読んだことで物語の世界を信用できるようになった?
村田:でも、やっぱり伝記だけでは我慢できなくなって、図書館に入り浸っていろいろ読んでいました。『赤毛のアン』とか『はてしない物語』とかも好きでした。『ホームズ』シリーズもハマりましたね。
物語の世界は、たまに洗脳しようとしてくる大人がいるって思っていただけで、基本的には一番信頼できる。要するに、会って話す大人が信用できなかったんですよね(笑)。でも、「本の世界は違う」って感じていました。
小説の世界の自由さに憧れた
──漫画やアニメではなく、本ばかり読んでいたのですか?
村田:アニメも好きだったし、漫画も読んでいました。ただ、図書室には漫画はないし、お小遣いもたくさんあったわけではないので……。
読んでたのは、むしろ少女小説。漫画みたいな挿絵があるような。『ゆうれいママ』シリーズとか『とんでる学園』シリーズ。中でも、窪田僚さんの『うらないトリオ・キューピッズ』っていうのがすっごく好きで。それを読んで、「少女小説家になりたい」と思って、自分で少女小説を書いていました。
──小学生の頃にはすでに小説を書いていたんですね!
村田:そうですね。兄が買っていた『シティハンター』とかを読んで憧れて、漫画も描いてみたんですけど、左向きの人しか描けなかったので(笑)。
──左向きしか描けないの、わかります(笑)。
村田:みんなおんなじ方向見ちゃうから、会話にならないんですよね(笑)。
小説って、「世界一の美女」って書いたら、いくら画力がなくてもそれは「世界一の美女」になるってことが、当時は「すごいことだなぁ」と思っていました。まあ、小説家になってみて、それは絶対にやっちゃいけないことだとわかったんですけど。
でもそのときは「想像したものが何でも描ける、すごく自由!」って思って。とても絵には描けないようなとんでもない生き物とか想像の世界も、小説では書ける。そういう自由さを感じて、小説にのめり込んでいったんだと思います。

──初めて書いたのはどんな物語だったか覚えていらっしゃいますか?
村田:ちゃんと完成させられたのは、同じ顔をした5人姉妹の話……いま思うとたぶん、その当時『おそ松くん』を観て影響されたのではないかと思うんですが(笑)。
当時から、キャラクターの似顔絵を描いたり服装を決めるのが好きで、末っ子は〈MILK〉の服を着て、長女は〈NICE CLAUP〉、四女はダイエーとか。いま考えると、姉妹間格差がひどいですね(笑)。洋服だけじゃなくて、歩き方とか文字の特徴とか、そういう設定を決めるのが昔から好きだったんですよね。
手で書くことでキャラクターと物語が動き出す
──いまでも物語を書き始めるときは、テーマやストーリーよりも、キャラクターから考え始めるんですか?
村田:似顔絵を最初に書くことが多いですね。でも、「差別を扱う」みたいな核心のテーマではなくて、ふんわりとしたテーマだけはそれより先に決めているかな。たとえば、『地球星人』*1だったら「長野が舞台」とか、『コンビニ人間』*2なら「コンビニが舞台」とか、それくらい。その次に、主人公の顔を描くことが一番多いですね。
*1『地球星人』……村田沙耶香さんの最新作。自分は魔法少女で、この世界を「人間を生産する工場」と考える主人公・奈月が、この世界のあり方の根本を問いかける衝撃作。2018年新潮社刊。
*2『コンビニ人間』……社会に適合できず、36歳になってもコンビニでアルバイトを続ける女性を主人公にした物語。2016年文藝春秋刊。第155回芥川賞受賞。

村田:こういう〈Campus〉のノートに、似顔絵を描いて。それから設定をどんどん書き込んでいく。これは短篇なので40枚綴りですが、長編のときは100枚綴りのノートを3冊くらい使うんです。
──3冊も!
村田:あとで何か思いついたときに書き込めるように、右側のページだけを使う癖があって、それもあって、すごいノート使っちゃうんですよね。
──最初はパソコンではないんですね。
村田:そうなんです、それはもう子どもの頃からで。小学生・中学生のときは、すごくたくさん小説を書いていて、受験のタイミングで一旦やめて、それでスランプになって。で、大学生になって純文学を書き始めたんですが、書き方はずっと一貫して、最初はノート。そのあとパソコンで打ち込んで、印刷したものにいろいろ書き込んで、書き込んだ部分をパソコンで修正して……その繰り返し
──手で書くのとパソコンで打つのでは、出てくるアイデアや言葉が変わるのでしょうか?
村田:手と頭って連結している気がして、タイピングの作業だけだと思いつかないんですよね、なんにも(笑)。手で書いていると、「この人はこのときこういう表情したんだ」「この先のシーンはこうだ」とか、「前のシーンこっちに持ってこよう」とか、どんどん思いつくんですけど、打ってるだけだと全然ダメですね。

賞狙いで“聖域を侵してしまった”トラウマ体験
──小学生の頃からずっと小説を書いていたとのことですが、そのときは賞に応募したりは?
村田:実は、あるできごとがトラウマになっていて……。中学生のときに、一度だけ講談社の「ティーンズハート」という賞に応募しようとしたことがあったんです。
その当時「ティーンズハート」レーベルでは、高校生の推理小説作家の方がすごく活躍されていて。アガサ・クリスティ好きの母も「この子は高校生なのにトリックがすごい」と褒めていて、それが羨ましかったのかな。「ああいう風になりたい」みたいな……「小説を書きたい」ではなく「小説家になりたい」という欲望にかられたんでしょうね、たぶん。それで自分も、推理小説は無理だけど、中学生作家として応募したいって思って。
小説って、私にとって本当に「聖域」だったんですよね。唯一、他人の顔色をうかがうことなく、小説と自分の喜びにだけ向き合えるというか。私、ワープロが小説の神様につながっていると思っていたんです。ワープロを通じて作品が神様のもとに届いて、神様がいいと思ったものが本になるシステムだと(笑)。それくらい、小説の世界って私にとっては教会のように神聖な場所だったんです。

村田:でも、そのとき、すごくあざとい気持ちになったんです。「大人が喜ぶ起承転結」みたいなものを狙って書いてしまった。そうしたら、それが本当に汚れた小説に思えたんです。作品のために作家が書いてるんじゃなくて、作家自身が愛されようとしてるってことが、自分にとっては最悪の、不誠実な作品でした。
その作品は、結局ゴミ箱に捨てて。本当は燃やしたいくらいだったんですけど。それで、もう賞とか勲章を狙うことはやめよう、小説を通じて愛されたいっていう気持ちは捨てようって思ったんです。神様と一緒にいられる時間を汚さないように。それからは、書くときにあまりなにも考えないようになりました。
──本当に書きたいことだけ、小説だけに向き合うようになったんですね。
村田:そうですね、それがよっぽどのトラウマだったので。でもありがたいことに、デビューしてからも「賞狙いなよ、村田さん」って言われたことってあんまりなくて。みんなから、「村田さんは賞なんて気にしなくていいんだよ」って言われる (笑)。でもそう言ってくれるのは、本当にありがたく思っています。
(後篇につづく)


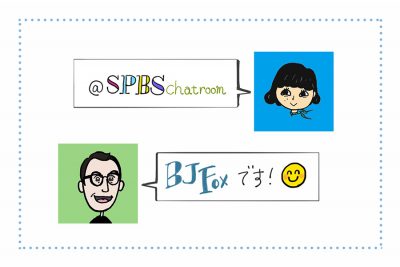

![物語の船で知らない世界にたどり着きたい──物語をつくる人#02 村田沙耶香さん[後篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2019/01/murata-2_eye-400x267.jpg)


村田沙耶香(むらた・さやか)さん
1979年千葉県生れ。2003年「授乳」で群像新人文学賞(小説部門・優秀作)受賞。2009年『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年「コンビニ人間」で芥川賞受賞。ほかに『マウス』『星が吸う水』『ハコブネ』『タダイマトビラ』『殺人出産』『消滅世界』など著書多数。近刊は、人間の性と生殖の欺瞞に鮮烈な光を当てる衝撃作『地球星人』(新潮社)。