![物語の船で知らない世界にたどり着きたい──物語をつくる人#02 村田沙耶香さん[後篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2019/01/murata-2_eye.jpg)
村田沙耶香さんへのインタビュー後篇では、小説で扱うテーマやストーリーをどのように考え、紡いでいくのかを伺いました。
世界の常識を問い直すような作品の数々は、どのように生まれてくるのでしょうか?
(前篇はこちら)
取材・文=志村優衣(SPBS)
写真=横尾涼
“女の子”としての苦しみから解放してくれた山田詠美さんの小説
──村田さんの作品は、性や家族にまつわる既存の価値観を解体していくようなテーマが多いですが、そうしたテーマを扱い続けている理由はあるのですか? たとえば、昔から「女性とはこうあるべき」みたいな価値観に違和感を持っていた、というような。
村田:先ほど(前篇)もお話ししたように、書き始めるときって似顔絵と「長野」「コンビニ」くらいのキーワードだけしかないので、なぜいつもこうなるのかっていうのは、私にもわからなくて(笑)。だから、あとから自分で分析するしかないんです。
でも、小さい頃から、女の子に生まれてきたことに対する喜びはありつつも、同時に苦しみも抱いていたと思いますし、それがものすごく大きな「書く理由」になっています。
──どんな苦しみか、お聞きしてもいいですか?
村田:子どもの頃から、「女の子としてがんばらなきゃいけない」という意識が強くて。たとえば、アニメの中に下着泥棒が出てきて、盗んだパンツがかわいい女の子のものじゃなくて、実はおばあちゃんのものだったことが判明したとき、みんなが「おえ〜っ」って言う、みたいなシーンがあったとして。そういうものを観たときに、「自分は『おえ〜っ』と言われる対象にはならないようにがんばらなきゃいけないんだ」みたいなことを、無意識に刷り込まれたことを覚えています。
パンツを盗むなんて最悪なことのはずなのに、それよりもパンツを盗んで喜んでもらえるような……男の子にとって性的魅力を感じる女の子にならなければいけないっていう、思い込みとプレッシャーがあった。それがしんどくて、だから純文学を書くようになったんだと思います。

──純文学の世界ならそうしたプレッシャーからの解放が可能だ、と感じたのでしょうか。
村田:高校生のときに山田詠美さんの小説を読んだことが大きかったと思います。山田さんの小説では、女性の性が「自分の身体は自分のもの。男の人のためのセックスじゃなくて、私のセックス」という風に描かれていたんです。
それまでは、自分の身体は人をよろこばせるための道具だと思っていたので、いい道具にならなければならないと思っていた。道具というのは、性愛という意味だけじゃなくて、おいしい料理をつくるとか、家事をやるとか、そうしたことがちゃんとできる「いい道具」。その「いい道具にならなきゃ」というプレッシャーに、長いこと苦しまされていたと思いますし、いまでもその苦しみは残っていますが、書くことで少しずつ楽になってきていますね。
──そうした苦しさから作品が生まれ、デビュー作の『授乳』*1につながったんですね。
村田:あの作品は大学のときにお付き合いしていた恋人が眠ってる横で、書いてたんです(笑)。すっごく嫌な母親が出てくるんですけど、あの母親は実は自分の投影で。このまま男の人に従属していたらこういう風になるんじゃないかって思いながら書いていたら、母親がどんどん化け物みたいになっていて。
──『授乳』のラストは、寝ている母親の胸の上にいる虫を踏み潰すシーンで終わりますよね。あのシーンは、自分を投影していた母親に「打ち克ちたい」というような気持ちが現れているのでしょうか。
村田:そうなのかもしれないです。当時はなんでこういうラストなのか、「自分でもわからん」と思っていたんですが(笑)。もっと自由な存在として生まれ変わりたいという気持ちが、ああいうラストを書かせたんじゃないかなぁ。
*1『授乳』……第46回群像新人文学賞を受賞した、村田沙耶香さんのデビュー作。潔癖症の母を持つ主人公が、家庭教師の先生とはじめた秘密のゲームとは? 2005年講談社刊。
小説の中に自分を追い詰める言葉を探している
──村田さんの作品には、最新作の『地球星人』もそうですが、「洗脳」というワードや「洗脳からの脱却」といったテーマがよく描かれています。それは、「こう振る舞うのが女性として正解」「こう生きるのが幸せな人生」というような価値観を当たり前のように受け入れてきて、思考停止状態に陥ってしまっている人たちに警鐘を鳴らしているのかなと感じていたのですが、読者にメッセージを送ろうという意識で書かれているのですか?
村田:それは、あんまりなくて。小説は、書いている間は自分と主人公と小説の神様の世界で、書き終えたら読者のものだと思っていて。だから、書いている間はそんなに読者のことは考えていないというか……。
私の小説って書き終えるとすごくメッセージ性がある感じになっているんですが、自分では「自由に読んでほしい」と思って書いています。私自身が、自由に読める小説のほうが好きで、読んだときに「この小説は自分のものだ」って思いたいんですよね。すごく好きな小説だと、そこに「作者がいる」ということが嫌で……だって、その大好きな小説を書いた作者がすごく嫌な人だったら、なんか嫌じゃないですか(笑)。だから、私の小説も書き終えたら読者のもの。「自分の小説」と思って読んでほしいと思っています。

村田:警鐘を鳴らしたいとしたら、読者に対してではなく自分に対してなんだと思います。自分の中に「追い詰めたい」部分がたくさんあって。無意識の差別とか、それこそ思考停止してしまっている部分を、ガンガンガンって目覚めさせて、「本当にそれでいいのか?」って言っている。だから、自分を追い詰める言葉が出てくるとホッとする(笑)。小説からそういう言葉を探している気がします。
“船で運ばれながら”書くと物語が作者を超えていく
──小さい頃からずっと小説を書いてきた中で、小説でしかできないことって、どんなことだと思いますか?
村田:他をあまりやったことがない中ではありますが、物語が読者を運んでいく感じ……私の場合は作家自身もですが、自分が物語の中の言葉に乗って一緒に運ばれていく感じというのは、小説特有のものだと思います。
──「運ばれる」というのは、「その世界に入りこむ」というイメージ?
村田:世界に入るのが最初にあって、そこから物語が川みたいに流れていって、その物語に沿って、船に乗って運ばれていくっていう感覚でしょうか。読むときも書くときも、「この船でまったく知らない場所にたどり着きたい」と思っていて。読書の仕方は人によって全然違うので、これは私なりの感覚ですが、私はその感じが好きなんです。
──ご自身が書いているときも、「船で運ばれながら」なんですね。
村田:そうですね。長野という舞台と主人公の似顔絵だけがある中で、「これでどこへ行くんだろう?」、「あ、こんなところに運ばれてしまった」みたいな。私が頭で考えてやること、意識下でやることって、まったく大したことができないんです。無意識の力を借りないと、物語を完成させることができないし……うーん、なんだろう。物語が作家を超えていく、物語が作家の想像ではまったく思いつかない世界へいかないとダメだと思っていて。
もちろん、賢い作家さんだったらそうでなくてもいいと思うんですけど、私は本当に凡庸な人間なので。私を超えたところに物語にジャンプしてもらわないと。でも、そのジャンプできる感覚は、私は小説の中でしか感じたことがないです。

──では、ラストを決めて、そこに収束させるような書き方はされない?
村田:それって、ラストシーンが最初から素晴らしいっていうことですよね? そういうのは、天才の人がやることなんだろうと思っています。
あと、言葉の力や無意識の力って、すごく強いんです。あの言葉を使うと連鎖反応的にこの言葉が生まれて、物語が紡がれていったりとか。無意識の力によって主人公が動き出す……たとえば〈MILK〉の服を着た子はザリガニは捕りにいかないけど、ダイエーの服を着た子はザリガニを捕るためにドブに入っちゃうとか。そうやって必然が生まれてきて、それによって連れていかれるラストに、私自身もびっくりするんです。
だから、最初からそのラストがわかる作家っていうのは、神的目線をお持ちですよね。そこから逆算して物語をつくれるというのは、本当に天才肌なんだと思います。
──お話を聞いていると、そうやって無意識下で物語を紡ぐことができる村田さんも、とんでもなく天才だと思います。ちなみに、「言葉」っていうところで一つお聞きしたかったのが、『地球星人』*2に出てくるあの、ポホ……ピアン……。
村田:あ、ポハピピンポボピア星人。
──はい。あの名前も、無意識のうちに生まれてきたんですか?
村田:そうですね。なんか、あれはもう言葉遊び的に。暗号とかでも、まったくなくて(笑)。
*2『地球星人』……村田沙耶香さんの最新作。自分は魔法少女で、この世界を「人間を生産する工場」と考える主人公・奈月が、この世界のあり方の根本を問いかける衝撃作。2018年新潮社刊。

──何か伏線があるんじゃないかとか、すごく考えちゃいました(笑)。
村田:残念ながら、まったくないんです。「ポ」とか「ピ」とかって、「宇宙人の音だな」って子どもの頃に感じていたので、子どもが遊んでつくったような名前になりました。「ポボピア星人くらいに縮めたほうがいいのでは?」とか、そういう話も最初は担当さんとしてはいたのですが、結局直さず(笑)。でも、あの長い名前だったからあのラストだったような気もしているので、あれでよかったと、担当さんも思ってくださっていると信じてます(笑)。
世界中の人たちと「文学の言葉」を交わしたい
──では最後に、これからどんなことをやってみたいかをお伺いできればと思います。
村田:これからの夢、そうですね……。『コンビニ人間』*3が翻訳されたっていうのが、自分の中でとても大きなできごとで。
──しかも、アメリカの雑誌『The New Yorker』の「The Best Books」と、イギリスの書店〈Foyles〉の「Book of the Year」に選ばれましたね! おめでとうございます。
村田:ありがとうございます。『コンビニ人間』が海外で読まれるなんて、まったく想像もしていなかったので、翻訳されて、しかも多くの人に読んでもらえたことがとても嬉しかったです。10月は翻訳家の竹森ジニーさんと、世界を周りながらイベントに登壇していて。ジニーさんのお話も素晴らしかったですし、海外の人が本当に作品を愛してくださっているんだなと再確認できたり、向こうの出版社の編集さんとも直接会って素敵な時間を過ごし、大切なお話をしたりして、すごく特別な時間を過ごしたんです。
そのおかげで、いまは海外のいろいろな人の顔が頭に浮かんでいて、「あの人たちにまた言葉をもらいたいな」って、飢えているんですよね。私がこれまで編集者さんとそっとしてきたような「文学の言葉のやりとり」を、海外の人としてみたい。文学の深い部分の話をもっとしたい。
昔から、「文学のことをもっと深く知りたい」「文学の言葉を交わしたい」という思いが強くて、それが書く原動力にもなっていたので。まったく違う文化の人たちと、「(村田さんの)作品読んだよ」なんて話ができたとしたら、また新しい発見があって、それが次の原動力になるんじゃないかなと思っています。そのためにも、次の作品も翻訳されて、翻訳され続ける作家になるのがいまの夢です。
──村田さんの作品が、世界の人たちにどう読まれるのだろうかというのは、読者としても非常に興味があります。
村田:ドキドキしますね(笑)。
──「世界の村田沙耶香」になっていくであろう、これからのご活躍を楽しみにしています!
村田:ありがとうございます。
*3『コンビニ人間』……社会に適合できず、36歳になってもコンビニでアルバイトを続ける女性を主人公にした物語。2016年文藝春秋刊。第155回芥川賞受賞。



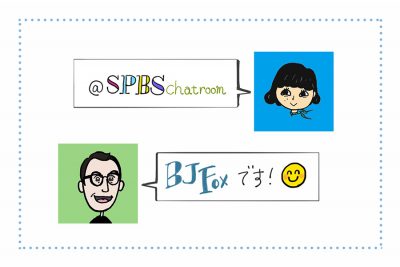

![小説の神様に向き合い続ける作家──物語をつくる人#02 村田沙耶香さん[前篇]](https://www.shibuyabooks.co.jp/spbs_cms/wp-content/uploads/2019/01/murata-1_eye-400x267.jpg)


村田沙耶香(むらた・さやか)さん
1979年千葉県生れ。2003年「授乳」で群像新人文学賞(小説部門・優秀作)受賞。2009年『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年「コンビニ人間」で芥川賞受賞。ほかに『マウス』『星が吸う水』『ハコブネ』『タダイマトビラ』『殺人出産』『消滅世界』など著書多数。近刊は、人間の性と生殖の欺瞞に鮮烈な光を当てる衝撃作『地球星人』(新潮社)。