
7月9日(木)に、SPBS本店が企画したイベント〈いま文芸誌があつい! [緊急開催]5大文芸誌が大集合! 文芸誌サミット〉をオンラインにて開催しました。当日は多くのお客さまにご視聴いただき、イベント中たくさんの質問が寄せられました。ご参加いただいたみなさま、改めてありがとうございました!
当日、時間の都合でお答えできなかった質問をいくつか選び、各編集部のみなさんにご回答いただきました。イベントの振り返りとしてお楽しみください。
各誌編集部プロフィール

『すばる』編集部(集英社)
岸優希(きし・ゆうき)さん
1990年生まれ。2015年に集英社に入社。新卒の配属より、『すばる』編集部所属。

わたしのこの1冊
『低地』(ジュンパ・ラヒリ 著/小川高義 訳/新潮社)
異国の地で暮らしていたことが、自分のなかのパーソナルな経験としてあって、初めて読んだときに震えました。クレストを創刊された恩師である松家さんの影響を受けているので、いつかこういう仕事がしたいなと思って編集を続けています。
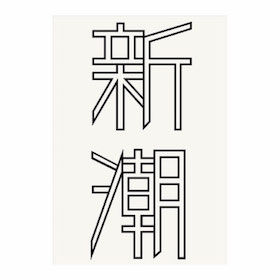
『新潮』編集部(新潮社)
杉山達哉(すぎやま・たつや)さん
1987年、岐阜県生まれ。2011年、新潮社入社。『週刊新潮』編集部、出版部文芸第一編集部を経て、2017年より現職。

わたしのこの1冊
『伯爵夫人』(蓮實重彦 著/新潮社)
出版部にいたときに担当した本。社内でも極秘で進めてきたプロジェクトで、最初に原稿を読ませてもらった瞬間、これはすごいぞと興奮しました。蓮實さんは批評家として長いキャリアのある方ですが、80代を目前にして、これまで使ったことのない語彙を使って作品を書かれたことにまず驚きました。ただでさえ話題になるだろうと直観しましたが、三島賞を受賞し、例の会見がニュースになったことで、仕掛けた火薬が当初の予想を超えて爆発。まさに事件を目の当たりにしたようで、忘れられない経験です。

『文學界』編集部(文藝春秋)
長谷川恭平(はせがわ・きょうへい)さん
1985年、山形県生まれ、2009年に文藝春秋に入社。週刊文春、電子書籍編集部などの編集を経て、2019年より『文學界』編集部。

わたしのこの1冊
『プレーンソング』(保坂和志 著 /中央公論新社)
読んだのはもう20年近く前になりますが、現代の純文学のおもしろさを最初に教わったのはこの本からだと思います。まじめな大学生ではなかった自分と容易に重なるようなダラダラした描写にどこか救われたような気がしたのを覚えています。物語の筋だけではない小説の奥深さ。何をやってもいいのだという可能性がひらけていくのを肌で、本当に感覚として肌で感じました。

『文藝』編集部(河出書房新社)
矢島緑(やじま・みどり)さん
1987年札幌市生まれ。幻冬舎、ポプラ社の文芸書編集部を経て、2019年1月河出書房新社入社、『文藝』編集部所属となる。

わたしのこの1冊
『親指Pの修業時代 上・下』(松浦 理英子 著/河出文庫)
大学3年生の時、ゼミの先生に薦められた本です。松浦さんの作品を読むのはこれが初めてで、ひっくり返るくらい面白かった。河出に入ってから席替えがあり、レジェンドのような先輩編集者の隣になりました。その方が『文藝』での「親指Pの修業時代」の連載担当だったと知り、その先輩の隣で働いていることが今も毎日うれしいです。
「文芸誌サミット」配信中にいただいた質問と回答
*質問はいただいた原文ママ掲載しております
Q1 一般の小説と比較した純文学の特徴・魅力はどのようなものとお考えでしょうか?
群像(森川)
純文学では、題材・テーマのおもしろさや時代性はもちろん表現の革新性に注目して読まれることが多いように思います。それは、いままで表現されたことのない世界であれば、これまでの文章表現では実現できず、それに即して表現の新しさも要請される、という考え方が共有されているからではないかと思います。私も時代をつくる作品は表現の新しさも含んでいると思います。
文學界(長谷川)
枠がないことではないでしょうか。そもそも純文学の定義(というものがあったとして)に曖昧な部分が大きいためこの話題は難しいのですが、ジャンルの枠に縛られない分、自由度が高いのが魅力ではないかと思います。エンタメであれば、話の筋というものはかなり重要視される部分ですが、純文学ではあらすじに要約できない作品も多いです(そういう作品が好きです)。もうひとつ純文学の特徴を言えば、それは私性のようなものではないかと個人的に思っているのですが(私小説というわけではなく)、そんなことを思うのは私が趣味で短歌をしているからかもしれません。
Q2 いま欲しい、逆に(現状は)もう十分だと思うのはどのジャンルですか?
すばる(岸)
どんなテーマも、ジャンルも、「書き尽くされる」ことはないのではと個人的には思います。そのテーマやジャンルの新しい見せ方、「こんな書き方があり得たのか!」という発見には、常に興奮し、感銘を受けています。
文藝(矢島)
こんな小説は読んだことがない、という衝撃を受けたい願望は常にあります。社会に確かに存在しているけれどまだ言語化されていない感覚や現象であったり、いないことにされている存在の声をすくいあげるような作品に、個人的には特に惹かれます。例えば新人賞の応募原稿等では家族やジェンダーについての作品が多い印象はありますが、そのテーマにどれだけ深く独自に接しているかを読みたいので、このジャンルはもう十分、というものはありません。
Q3 文芸誌編集者ならではの職業病(のようなもの)はありますか?
新潮(杉山)
例えば、音楽を聴きながらそのミュージシャンは小説を書きうるだろうか、演劇を見ながらそのつくり手は小説を書きうるだろうかといったように、他のジャンルの作品と向き合うときにも常に並行して潜在的な「作家」を探してしまっているかもしれません。そのため、耳から受け取った言葉を頭の中では文字に書かれた形に変換して捉える癖があります。
すばる(岸)
明確に職業病というものはないですが、小説家以外の表現をなりわいとされている方の文章(ソーシャルメディアのテキストや雑誌のコラムなど)は、つい、「文芸誌に寄稿していただけそうだろうか?」という観点で読みがち、ではあると思います。
Q4 新人賞受賞は単行本化して欲しいのですが、できない時もあると思います(新潮社さんとか)そこらへんの事情を知りたいです
新潮(杉山)
芥川賞・三島賞など大きな文学賞の候補になった場合を例外として、基本的にいま新潮新人賞からデビューした書き手は、何作か雑誌に作品を発表したのち初めて単行本が出ます。そこにはもちろん営業上の判断もありますが、単行本化を見据えて継続的に書いてもらい、厳しい評価にさらされることが、新人作家の筆力を高める一番の近道になるものと考えています。
文學界(長谷川)
もちろん新人賞受賞作は本にできることが望ましいですが、昨今の出版事情からなかなかすべてを単行本化することは難しい状況です。たとえば文学賞の候補になるとか、作品で書かれている内容が時流にあっているであるとか、作品の良し悪しとは別の要素も関わってきます。そもそもこれらは営業と書籍の編集部が決めることですので、私ども雑誌の編集部員にもあずかり知らない事情があると思います。
Q5 「活字」や「余白」など、紙面デザインへのこだわりやまなざしなどはありますか?
群像(森川)
イベント当日にもお話しましたが、デザイン・リニューアルを担当している川名潤さんには表紙だけでなく、雑誌全体を見てもらっています。たとえば書評ページひとつとっても今号(9月号)ではマイナーチェンジしています。川名さんと仕事をしているとそのディテールへの配慮に驚かされ、いつも勉強になります。川名さん自身による「極私的雑誌デザイン考」という連載もありますので、ぜひご覧ください。
文藝(矢島)
雑誌は、いろんなものがぎゅっと1冊にまとまっているところがおもしろいですよね。文芸誌であれば、長短さまざまな小説やエッセイ、対談、論考、企画ページ、連載などがあります。とにかく文字量は多い(多いときは1号70万字とか)ですから、飽きずに楽しくページをめくっていただきたく、ADの佐藤亜沙美さんと相談しながら緩急をつけたデザインを意識しています。
Q6 最近の他社の企画ですごいな!と思ったものがあれば教えてください。
新潮(杉山)
『文藝』秋季号の特集「覚醒するシスターフッド」、『群像』7月号の特集「「論」の遠近法」には、編集者として大いに刺激を受けました。ベテランから若手まで様々なタイプの書き手が時宜を得たテーマや特集の枠組みによってひとつになっていて、時には与えられたお題自体を問い直すような視線も含め、まさに雑誌的な面白さが現前していたように思います。
すばる(岸)
『文藝』の秋季号。「覚醒するシスターフッド」のほとばしるエネルギーにも刺激を受けましたし、「非常時の日常」の作家たちの日記から立ちのぼる現実の豊かさにも揺さぶられました。「いま」を誌面で見せるとはこういうことかと、勉強になりました。
Q7 フェミニズムなどのホットで論争を生みやすいトピックを出版する上で、文芸誌としての社会的責任や役割はどのようにお考えですか。
文學界(長谷川)
たしかに話題のトピックを取り上げることは多いですが、そこに社会的責任があるかといわれると難しいです。そういった大枠でとらえられない個々の問題を一つひとつ掬い上げること、むしろそれこそが文芸誌の責任ではないでしょうか(責任というものがあるとして)。先の純文学云々の話とも通じますが、小説にしろ評論にしろ、明快なテーマでは縛ることのできない作品はたくさんあります。そういった事象を拾い上げること、いい作品をつくり上げることにこそ力を注ぎたいです。あくまで個人的な思いです。
文藝(矢島)
スピードを重視すればネットがありますから、文芸誌は数十年後の人が読むときに、この時の「いま」はこうだったんだと伝える記録媒体の役割もあると思います。創作や特集を通して、いま起きていることを検証し、書き手、読み手、編集がみんなで考えられるような場でありたいです。国内外の、新しい書き手の挑戦作と熟練の作家の作品を同時に味わえる1冊をお届けします。
Q8 雑誌本体の広告を見ると、特に『すばる』(〈救心〉)など対象年齢が高そうな雰囲気があるのですが、対象読者はどのように意識なさっていらっしゃるのでしょうか。また、若い人に向けた雑誌作りの意識などがあればお聞かせ願いたいです。
すばる(岸)
定期購読をしてくださっている方々の年齢層が高めなので、広告も必然的にそのような内容になっているのではと思います(〈救心〉は、小誌に限らず、文芸誌の定番の広告ですよね)。新しい読者を獲得するために試行錯誤をするなかで、現代/社会と直結するような特集を提案することはいつも心がけています。
文學界(長谷川)
対象年齢ということはあまり考えていません。特に文芸誌が高年齢層に向けた雑誌だという認識は持っていませんでした(広告についてはまた別の事情があるのだと思います)。編集部の人員構成も30代40代しかいませんし、同年代の読者が読んで面白いものにはなっているのではないかと思います。むしろ高年齢層の読者が読んで面白いものになっているのかというところをあまり考えていなかったなと、質問をいただいてふと思いました。
Q9 純文学雑誌以外で掲載小説を気にして読んでいる雑誌は?
群像(森川)
柴田元幸さんが編集長をつとめておられる『MONKEY』や『SFマガジン』『小説すばる』『小説現代』などを読んでいます。単行本で初めて知る作家も多いです。
新潮(杉山)
「純文学雑誌」というわけではないものの、柴田元幸さんが編集長を務める広義の文芸誌である『MONKEY』は、毎号注目して見ています。最新号にはブレイディみかこさんによる初小説が掲載され、やられた! と思いました。また、一昨年のリニューアル後の『WIRED 日本版』は以前より文芸色が強まり、気になる存在です。
文藝(矢島)
今回の5誌以外でしたら、『小説トリッパー』『ユリイカ』『MONKEY』『中くらいの友だち』など、新しい号が出ると定期的に手に取っています。媒体で選ぶというよりは、気になる作家の原稿が載っていたり、話題になっている作品があるとそれ目当てで読むことが多いです。
Q10 「創作合評」をいつも楽しみにしております。合評を見て、新しい作家や作品の存在を知って、本を買うことがよくあります。よい作品はたくさんあると思いますが、合評に取り上げる作品は、どんなプロセスで決まるのでしょうか。
群像(森川)
毎月発売される(もちろん季刊、不定期刊のものもあります)文芸誌を部員それぞれが全部読みます。その後、会議を経て取り上げる作品を3作程度決定します。評者はいまは3ヵ月ごとに替わります。その組み合わせだったり、面白さを考えて、どの作品を取り上げるかを話し合います。作品数の多い月もあれば、少ない月もあるので、多い月は悩ましいです。なるべく群像新人のかたの作品を取り上げたいという思いはあります。
Q11 挿絵はどのように決めますか?
新潮(杉山)
弊誌では、小説作品の扉ページに「カット」として、写真もしくはイラストを載せています。編集部員の持ち回りで毎号ひとりのアーティストに依頼しており、8月号では映像作家・小田香さんにメキシコ滞在時のスナップを寄せてもらい、9月号には写真家・志賀理江子さんが宮城県で撮った作品を掲載しました。ここも同時代の最先端の表現の場としてご注目いただけたら。
Q12 『文藝』では同時代の海外作品も積極的に載せていく、というお話がありましたが、他の4誌では、海外作品を載せることについては、どれくらい積極的に考えていますでしょうか?
新潮(杉山)
短篇作品を中心に海外文学の掲載も積極的にできればと考えており、自社で展開しているレーベル〈新潮クレスト・ブックス〉と連動して動くことが多いです。最近もコロナ禍を受けて書かれたテジュ・コール「苦悩の街」(木原善彦訳、6月号)や、ポール・オースター「スタニスラーウの狼」(柴田元幸訳、7月号)を、いち早くご紹介しました。
Q13 保坂和志さんと山下澄人さんの対談が聴きたいです。
新潮(杉山)
いまから数年前のもので、ひょっとしてすでにご覧になっているかもしれませんが、『しんせかい』の刊行を受けた山下澄人さんと保坂和志さんの対談を弊誌に掲載しています。対談原稿はこちらでも読むことができますので、もしよろしければ。
Q14 そろそろ各社文藝と新潮は新人賞受賞が決まるころですか??
新潮(杉山)
この回答を書いている現在(7月中旬)は、編集部による下読みの大詰めの段階です。三段階の選考で今年は12作にまで絞られた応募作を編集部全員で読み、7月末の会議で最終候補5作を選びます。そして8月頭に候補作を選考委員5氏にお送りし、9月上旬の選考会で受賞作が決定する───というのが例年の流れです。受賞作は10月発売の11月号に掲載予定。どうぞご期待ください!
各編集部のみなさんが最近関わった本
群像(森川)
ブレイディみかこさんの「ブロークン・ブリテンに聞け Listen to Broken Britain」、三浦哲哉さんの「LA・フード・ダイアリー」の連載が完結し、単行本化の予定です。
すばる(岸)
中村佑子さんの連載「私たちはここにいる——現代の母なる場所」が完結し、武田砂鉄さんの連載「マチズモを削り取れ」もまもなく最終回で、それぞれ単行本化予定です。
新潮(杉山)
高山羽根子さんの『首里の馬』。コロナ禍により世界が変貌しつつあるいま、すべての本を愛する人、知識を求める人に読んでほしい一冊です。10月号には『これは小説ではない』を刊行したばかりの佐々木敦さんと高橋源一郎さんによる対談を掲載。原稿を構成しながら自分自身も「小説」の概念が拡張される、刺激的な内容になりました。
文學界(長谷川)
発売中の文學界9月号に掲載された小説では、滝口悠生さん「アッパとアンマのピリピリ・クッキング」と砂川文次さん「小隊」を担当しました。前者はスリランカ生まれでロンドンで生活している夫婦が日本は小伝馬町のマンションの一室で自慢の手料理を作るという、その工程がつぶさに描かれます。料理中のふたりの所作ひとつひとつが尊さをもって描かれており感動的です。後者はパラレルな日本を舞台に、北海道に攻め入ってきたロシア軍を自衛隊が迎え撃つというスリリングな戦争小説です。
また巻頭には歌人の𠮷田恭大さん(いぬのせなか座・刊『光と私語』はすばらしい歌集です)に短歌10首を寄稿いただきました。コロナ禍の日常、篠田優さんの写真とあわせてご鑑賞ください。
文藝(矢島)
それぞれ『文藝』に一挙掲載した大前粟生さん『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』、山下紘加さん『クロス』、倉数茂さん『あがない』などを担当しています。今号に掲載している、昨年『かか』で文藝賞を受賞しデビューした宇佐見りんさんの第2作『推し、燃ゆ』を9月に、王谷晶さん『ババヤガの夜』を10月に単行本化します。







『群像』編集部(講談社)
森川晃輔(もりかわ・こうすけ)さん
1989年生まれ。2013年に講談社に入社。週刊現代、FRIDAY編集部を経て、2017年より『群像』編集部。
わたしのこの1冊
『アウステルリッツ(新装版)』(W・G・ゼーバルト 著/鈴木仁子 翻訳/白水社)
高校生のときに読んでとても面白かった。その本が、今回新装版で出版された。講談社にBundanTVというYoutubeチャンネルがあり、そこに「出版社社員がオススメする他社本!」というコーナーがあり、そちらでも詳しく紹介しています。